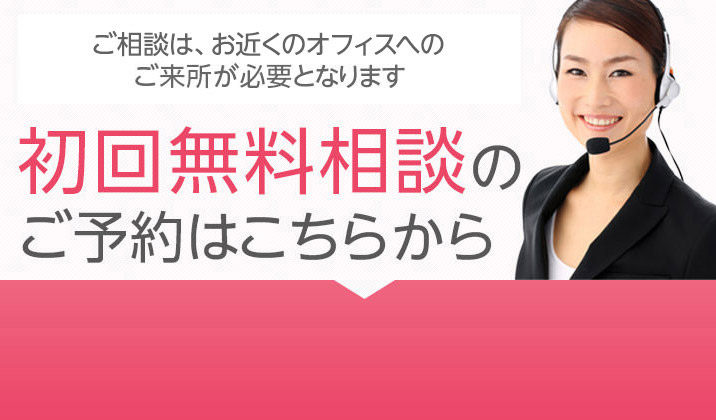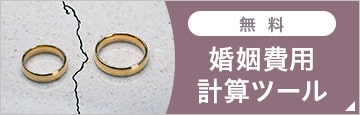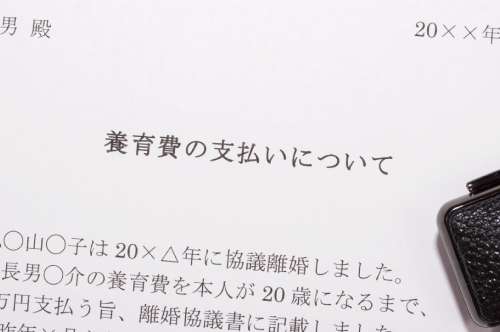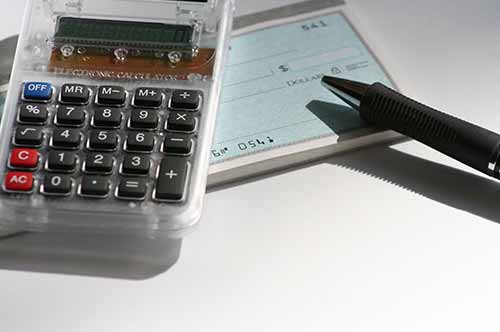デートDVとは? 婚約者や恋人から暴力を受けたときに行うべき対応方法
- その他
- デートdv
- 法律

配偶者から受ける暴力についてはDV(ドメスティックハラスメント)として広く知られるようになりました。他方で、婚約者など交際相手からの暴力や暴言についても、「デートDV」として知られつつあります。
実際に、町田市のサイトでも配偶者や交際相手からのDVに悩む方に向けた相談窓口の案内が行われています。DV被害を受けているとどの状態が正常であるかわからなくなってしまいがちです。苦しんでおられるのであれば、すぐに公的な相談窓口をご活用ください。
本コラムでは、デートDVの定義から、婚約者や恋人からDVの被害に遭っている方はどう対応すべきなのか、法律的にはどのようなことができるのか、さらには「別れる」と告げたら「婚約破棄だから慰謝料を請求する」などと言われたらどうすべきかについて、ベリーベスト法律事務所 町田オフィスの弁護士が解説します。


1、デートDVとは
「デートDV」は家庭内のDVと何が違うのか、どういった行為が該当するかなど、まずは基本的な内容をご説明します。
-
(1)デートDVの定義
デートDVとは、交際相手との間で起きる暴力等のことです。
DVはDomestic Violenceの略で、これまでは夫や妻、親、子どもなどから受ける家庭内のさまざまな暴力等をさしていました。
近年、暴力は配偶者など家庭内だけではなく、交際相手との間でも起きているということが知られ、「デートDV」という言葉が使われるようになりました。
内閣府が令和5年に公表した「男女間における暴力に関する調査報告書」によると、交際相手からデートDVを受けた経験がある人の割合は、女性で22.7%、男性で12%もおられます。さらに、デートDVを受けたことがある方のうち、交際相手との同居期間中に被害を経験した方は、全体で77.8%もおられました。
今まであまりクローズアップされませんでしたが、被害を受けている方は非常に多いのです。 -
(2)デートDVの5種類の暴力
デートDVに該当する行為は、主に次の5種類です。
- 身体的暴力
- 精神的暴力
- 経済的暴力
- 性的暴力
- 社会的隔離
それぞれ詳しくご説明します。
-
(3)身体的暴力
DVとして、まず思い浮かぶのが身体的な暴力でしょう。
殴る、蹴る、髪を強く引っ張る、物を投げつける、タバコの火を体に押し付けるなどの行為が該当します。
暴力がひどい場合には骨折や火傷などのケガを負うこともあります。 -
(4)精神的暴力
精神的暴力とは大声で怒鳴る、無視をする、脅す、人前でバカにする、大切にしているものを壊す、といった相手の心を傷つける行為です。
「お前はバカか?」「頭がおかしいんじゃないか?」「従わないなら会社に秘密をバラす」といった発言で相手を従わせ、精神的に追い込みます。
被害が続くとPTSD(心的外傷後ストレス障害)になってしまうこともあります。 -
(5)経済的暴力
暴力として認識していない方も多いと思いますが、お金が関係する行為も暴力に該当します。
たとえば相手に借金をさせる、借りたお金を返さない、毎回デート代を負担させる、無理やり高額なプレゼントを買わせる、アルバイトをさせてお金を貢がせるなどの行為です。 -
(6)性的暴力
たとえ交際相手であっても、相手が嫌がる性的な行為は暴力にあたります。
具体的には無理やり性行為をする、同意なく避妊しない、中絶させる、見たくもないアダルトビデオを見させる、勝手にわいせつな動画を撮るといった行為です。
内容によっては不同意性交等罪(旧 強制性交等罪(刑法第177条))などの犯罪にあたる可能性もあります。 -
(7)社会的隔離
社会的隔離とは、広く言えば「束縛」です。
たとえば携帯電話を勝手にチェックする、外出を制限する、異性としゃべらせない、人付き合いを制限する、メールにすぐ返信するように強要する、といった行為です。
相手を監視下に置き、束縛して自分の思い通りにさせようとします。
2、デートDVに関する法律
デートDVは放置すれば重大な事件に発展する可能性があります。そこで、DVを受けている方を被害から守るために、法律でさまざまな対応策が定められています。
-
(1)DV防止法
DVに関する代表的な法律が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法、DV防止法)」です。
この法律では配偶者からの身体的、精神的・性的暴力の防止と、被害者の保護、自立支援などを広く定めています。実情に即して少しずつ改正されており、直近では令和5年にも改正され、令和6年4月1日から施行されています。
DV防止法の中でも重要な規定が「保護命令」に関するものです。
保護命令とは、身体的暴力や生命に対する脅迫を受けた際に、被害者の裁判所への申し立てにより発令される、加害者の行動を制限する命令のことです。
次の4つの保護命令を定めています。
- 被害者への接近禁止命令:被害者へのつきまといや、家や職場の近くのはいかいの禁止
- 被害者の子どもや親族への接近禁止命令:被害者の子どもや親へのつきまといや、家や学校などの周辺のはいかい禁止
- 電話等禁止命令:暴言や無言電話の防止のため、加害者から被害者に対する面会の要求、電話やFAX、メール等を送信することの禁止
- 退去命令:被害者が加害者と同居している場合、被害者が同居する住居から引越しをする準備等のために加害者に原則2か月間、家から退去することを命じ、かつその期間その家をうろつくことの禁止
被害者が申し立てをし、裁判所が認めれば保護命令が発令されます。
保護命令に違反した場合、令和6年3月31日までの行為のときは1年以下の懲役または100万円以下の罰金が、法改正に伴い令和6年4月1日以降であれば2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されます(DV防止法第29条)。
また、法改正前までは身体的な暴力や命や体に危険を感じる脅迫のみ命令の対象となっていましたが、法改正した現在は身体に対する暴力だけでなく、「生命又は身体」に対して加害者から脅迫を受けたケースや、「自由、名誉又は財産」に対して加害から脅迫を受けたケースも含まれることになりました。
かつてのDV防止法は、結婚している夫婦のみを対象としていましたが、平成25年に同棲中の交際相手や事実婚の夫婦、離婚後の配偶者にも適用できるように改正されました(DV防止法第28条の2)。
結婚を前提で婚約し同居している状況でデートDVを受けている場合には、申し立てをすることで保護命令を出してもらえるかもしれません。
また、DVの内容によっては、刑法の暴行罪(刑法第208条)や傷害罪(刑法第204条)などに該当するとして、警察に相手を逮捕してもらえる可能性もあります。 -
(2)ストーカー規制法
デートDVには「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」の規定が適用できる可能性があります。
ストーカー規制法は、つきまといやストーカー行為の規制と、被害者への援助を定めた法律です。
次の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、繰り返した場合には「ストーカー行為」にあたるとしています。
- つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、うろつき等
- 監視していると告げる行為
- 面会や交際の要求
- 乱暴な言動
- 無言電話、連続した電話・FAX・メール・SNS等
- 汚物などを送る
- 相手の名誉を傷つける
- 性的羞恥心の侵害
ストーカー行為をした場合の罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(ストーカー規制法第18条)。
つきまといやストーカー行為があった場合、警察は加害者に警告(ストーカー規制法第4条)や禁止命令等(ストーカー規制法第5条)をだすことができます。
暴行や脅迫等の刑法上の犯罪が成立すれば、逮捕される場合もあります。
3、デートDVの相談窓口
デートDV被害者の中には「家族や友人には言えない」「相談したいが、相手にバレるのが怖い」と思い、一人で抱え込んでしまっている方もいるでしょう。ですが、そのままでいても状況の改善は見込めません。まずは次の相談先に連絡してみてください。
-
(1)どうすべきか迷ったら自治体の相談窓口
全国の都道府県や市町村には「配偶者暴力相談支援センター」の機能の施設が設置されています。
東京都では東京都女性相談センターと東京ウィメンズプラザ(生活文化局)が「東京都配偶者暴力相談支援センター」としての機能を担い、電話や面接で相談ができます。
センターではDVに関して以下のような支援を行っています。
- 相談
- カウンセリング
- 緊急時の安全確保、一時保護
- 被害者の自立支援
- 保護命令や保護施設に関する情報提供と支援
配偶者からだけでなく、交際相手からの暴力も相談できます。
-
(2)刑事告訴するときは警察
都道府県警察には、犯罪被害の相談窓口が設置されています。
デートDVはDV防止法違反やストーカー規制法違反以外に、刑法の暴行罪や傷害罪などに該当する可能性があります。
交際相手からのDVでケガをした場合などは、すぐに警察に相談しましょう。 -
(3)刑事告訴・婚約破棄をしたいときは弁護士に相談
相手から暴行などを受けている場合は、前述のとおり、暴行罪や傷害罪などに該当する可能性があります。その場合、被害を受けた方は加害者を刑事告訴することができます。
相手を刑事告訴したい場合、弁護士が代理人として告訴します。
刑事告訴を検討している方は、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
他方で、婚約者からDVを受けている方で婚約破棄をしたいとお考えになっている方も、弁護士に相談すべきです。場合によっては、すでに婚約しているからこそ「別れると言ったら慰謝料を請求する」と脅されている方もいるかもしれません。
しかし、婚約破棄に至った責任はDVをする加害者にあります。したがって、あなたが相手に慰謝料を請求できる可能性が高いのです。ただし、慰謝料請求を行うためには証拠が必要となります。婚約破棄をして慰謝料を請求したい方や、DVから逃げるために婚約破棄したら慰謝料を請求された方は、できるだけ早く弁護士に相談してください。
依頼を受けた弁護士は婚約解消に向けた適切な進め方についてアドバイスを行うとともに、相手との交渉をすべて弁護士が行うことが可能です。あなた自身が対応する必要はありません。
お問い合わせください。
4、まとめ
交際相手からのDVは、心にも体にも傷をつけます。「自分が悪い」と思っている方もいるかもしれませんが、悪いのはDVをする相手です。DVはエスカレートする可能性もあるため、なるべく早く自治体の相談窓口や警察、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
弁護士はお客様のお話を親身になってお聞きし、お客様を守るために迅速に行動します。DVの証拠がない、相手と直接話をするのが怖いといった場合も、弁護士が代わりに対応します。全力でサポートしますので、まずはベリーベスト法律事務所 町田オフィスまでご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|