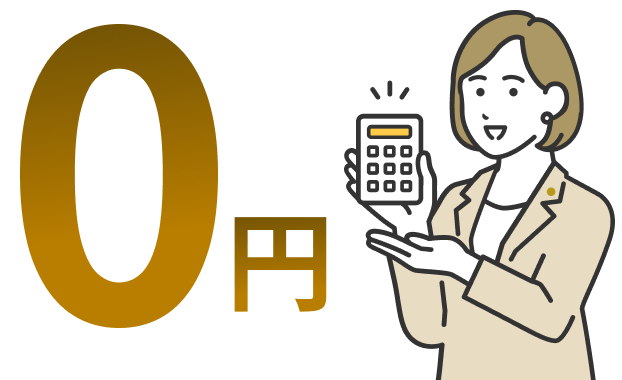子どもがいない夫婦の相続問題を町田の弁護士が解説
- 遺産を受け取る方
- 子どもがいない
- 相続

ベッドタウンとして発展し、人口が多い町田市でもやはり近年の人口減少の傾向は見られ、人口の自然増加率は減少率よりも低い水準を保っています。そのような中で、子どもがいない夫婦は珍しくはないでしょう。とはいえ、夫婦のどちらかが亡くなった後の遺産相続については誰が相続するのかが問題になりやすく、しばしば相続争いに発展することがあります。
配偶者がすべての財産を相続できればそれで話が済むのですが、配偶者以外にも相続できるケースがあるからです。そこで今回は、次の相談事例を元に、子どもがいない夫婦の相続について町田の弁護士が解説します。
「わたしの叔母(父の妹)の夫が亡くなりました。叔母夫婦には子どもがいませんが、姪であるわたしや父には相続する権利があるのでしょうか。それとも、叔母がすべて相続するのでしょうか。」
1、相続で知っておきたい基礎知識
まずは相続について、押さえておくべき基本的な項目について解説します。
-
(1)法定相続人とは
法定相続人とは、民法という法律によって定められた、相続財産を受け取ることができる権利者のことです。
被相続人(亡くなった人)の配偶者は必ず相続人となり、「配偶者相続人」といいます。
その他の相続人については「血族相続人」と呼ばれ、次のように、グループごとの順位が決まっています。- 第1順位……直系卑属(子ども、孫)
- 第2順位……直系尊属(父母、祖父母)
- 第3順位……兄弟姉妹
子どもがいない夫婦のどちらかが亡くなった場合、配偶者がすべての財産を受け継ぐかといえば、必ずしもそうではありません。通常は、配偶者と血族相続人のうち順位が上位の者の組み合わせで、遺産を分けるケースが多くなります。
-
(2)法定相続分とは
さらに民法では、財産の取り分の割合を「法定相続分」として定めています。法定相続分は、法定相続人の組み合わせによって次の割合になります。
- 配偶者のみ……100%
- 配偶者+直系卑属……配偶者1/2、直系卑属1/2
- 配偶者+直系尊属……配偶者2/3、直系尊属1/3
- 配偶者+兄弟姉妹……配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
ここで登場する「直系卑属(ちょっけいひぞく)」とは、被相続人の子どもや孫などが該当します。たとえ実際の血のつながりはなくとも、戸籍上の子どもである養子も直系卑属に該当します。続いて「直系尊属(ちょっけいそんぞく)」とは、被相続人の父母や祖父母などが該当します。もし被相続人が養子縁組をしているのであれば、戸籍上の養父母も直系尊属に含まれることになります。
法定相続分では、被相続人の配偶者がすでに死亡している場合、もっとも順位が上の血族相続人が単独で相続します。たとえば、子どもと祖父母がいた場合、第1順位者は子どもですので、子どもがすべて相続します。「子ども+祖父母」という取り扱いにはなりません。
2、子どもがいないときの相続
被相続人に配偶者と子どもがいれば、通常は、配偶者と子どもが遺産を相続することになります。その場合は、相続トラブルに発展しにくいといえますが、問題は子どもがいないケースです。
配偶者にとって、被相続人の父母や兄弟姉妹は血のつながりがない方たちであり、逆の立場からしても同じことがいえます。関係が良好であったとしても、配偶者が亡くなったことで相続争いに発展するケースは多々ありますので、法律上の決めごとをよく押さえておくことが大切です。
ここで、もう一度冒頭にあげた質問を確認してみます。
「わたしの叔母(父の妹)の夫が亡くなりました。叔母夫婦には子どもがいませんが、姪であるわたしや父には相続する権利があるのでしょうか。それとも、叔母がすべて相続するのでしょうか。」
登場人物を次のように設定して子どもがいない夫婦の遺産相続について、具体的に見ていきましょう。
- わたしの父(被相続人の配偶者の兄)=A
- 相談者であるわたし(被相続人の姪)=A1
- わたしの叔母(被相続人の妻)=B
- 叔母の夫(死亡した被相続人)=B1
- 叔母の夫の父母(被相続人の父母)=B2
- 叔母の夫B1の姉(被相続人の姉)=C
- 叔母の夫B1の姉の子ども(被相続人の姉の子)=C1
-
(1)故人の父母が健在であるとき
まずは、叔母の夫B1の父母B2が健在だったケースを想定します。
叔母Bは、被相続人の配偶者であるため、当然に相続人となります。叔母夫婦には第1順位の子どもや孫がいませんので、第2順位である父母B2が相続人になります。このケースでは、配偶者である叔母Bと、夫B1の父母B2に財産を受け取る権利があるわけです。
相続割合は、「配偶者+直系尊属」となるため「配偶者2/3、直系尊属1/3」となります。仮に財産が3000万円であれば、叔母Bが2000万円、父母B2が1000万円受け取ることになります。
結果、姪であるわたしA1や、わたしの父Aは財産を受け取ることができません。 -
(2)故人の父母が他界しているとき
では、叔母の夫B1の父母や祖父母がすでに亡くなっているときはどうでしょうか。このときは、第3順位グループの兄弟姉妹が浮上します。
今回のケースでは、相談者であるわたしにとって、叔母の兄にあたるA(わたしの父)が相続できそうな気がするかもしれません。しかし、Aは、被相続人B1の兄ではなく、あくまでもその配偶者Bの兄です。被相続人の兄弟姉妹ではありませんので、そもそも法定相続人にはなりません。
相続発生時に被相続人の父母が他界しているときは、B1の実の姉であるCに相続権が発生します。Cがすでに亡くなっている場合は、代襲相続によって、Cの子どもC1が財産を受け取ることになります。
本ケースにおける相続割合は「配偶者3/4、兄弟姉妹1/4」です。仮に財産が3000万円だったとすると、叔母Bが2250万円、被相続人の姉Cが750万円受け取ることになります。
したがって、どちらのケースでも、姪であるわたしA1には相続権は発生しません。
3、法定相続人以外が相続できるケース
前述のとおり、今回のケースでは被相続人にとっていわば「義理の姪」にあたるA1は、法定相続人になりません。
しかし、被相続人とA1に親交があった、もしくは特別に世話をしていたなどの場合には、少しでも財産をもらいたいと考えることがあるかもしれません。ここからは、法定相続人ではない「わたし」、つまり被相続人からみて義理の姪が財産を受け取れる可能性があるケースを紹介します。
-
(1)遺言書がある場合
故人の意志を残した遺言書がある場合、義理の姪A1にも相続できる可能性がでてきます。
遺言書は被相続人が特定の者に相続させたい場合や、遺族のもめごとを避けたいときなどに作成されるもので、その死後も尊重されるからです。
ただし、遺言書に「義理の姪であるA1にすべての遺産を与える」と書かれていた場合であっても他の相続人から遺留分請求をされる可能性はあります。
遺留分とは、一定範囲の法定相続人について、最低限の遺産の取り分を確保できる制度です。遺言書の存在によって、本来であれば財産を受け取れる近親者の生活基盤が失われてしまう危険性が発生する場合があります。一方で、故人の意思も尊重するべきといえます。そこで民法では、遺言書に優先し、一定の取り分を主張する権利を認めているのです。
遺留分が認められるのは次の者です。- 配偶者
- 直系卑属(子ども、孫)
- 直系尊属(父母、祖父母)
兄弟姉妹は法定相続人にはなれますが、遺留分権利者にはなれません。ここはよく混同されやすい部分ですので注意が必要です。
なお、遺留分の割合は以下のとおりです。- 配偶者のみ……1/2
- 配偶者+直系卑属……配偶者1/4、直系卑属1/4
- 配偶者+直系尊属……配偶者2/6、直系尊属1/6
- 直系卑属のみ……1/2
- 直系尊属のみ……1/3
叔母Bには子どもがいませんので、父母や祖父母が他界していれば、財産の1/2を遺留分として主張できます。つまり、「義理の姪A1にすべて相続させる」という遺言書があったとしても、叔母Bが遺留分請求をすると、叔母Bが1/2、残りの1/2をA1が相続するというわけです。
-
(2)生前贈与
故人が死ぬ前に、自分の財産を先に贈与しておくことです。ただし、これも遺留分請求を受ける可能性はあります。
-
(3)叔母Bが相続した後に死亡したとき
叔母Bが、配偶者からの遺産の一定分を相続した後に亡くなった場合は、すでに財産が叔母Bのものになった後の話になります。そのため、Bの実兄であるAや、姪であるA1にも財産を受け取れる可能性が生まれます。
叔母Bには子どもがおらず、父母や祖父母が死亡していれば、実の兄であるAに相続権が発生します。さらにAが亡くなっていれば、姪A1が相続人になるということです。このように、直接的ではないにしろ、財産がまわりまわってA1の元にくる可能性はゼロではありません。
4、まとめ
今回は、子どもがいない夫婦の相続について解説しました。
相続問題はお金が絡むことですし、権利があるのかないのかでもめることもあります。関係者全員が、納得のいく形でおさまるケースばかりではなく、数年にわたる紛争状態になってしまうことは珍しくありません。
しかし、お金のことで争いが起きることは、故人が望んだ結果ではないはずです。相続問題に対応した経験が豊富な弁護士に早い段階で相談することで、円満な解決を目指す方がよいのではないでしょうか。
ベリーベスト法律事務所 町田オフィスでは、子どもがいない場合の相続について、弁護士が随時ご相談をお受けします。トラブルになりそうなときや、納得できないことがあるときは、ぜひ気軽にお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています